日本の中小企業は、地域経済と雇用を支える重要な存在である一方、近年は「事業承継」が大きな課題として浮き彫りになっています。中でも深刻なのが、経営者の高齢化です。中小企業の代表者の平均年齢はすでに60歳を超え、引退時期を迎える経営者が増加しています。しかし、そのタイミングで事業を引き継ぐ「後継者がいない」企業が非常に多いのが現状です。調査によれば、後継者不在率は依然として約半数に達し、後継者探しができないまま経営者の高齢化だけが進むという、深刻なミスマッチが起きています。
さらに問題を複雑にしているのが、黒字廃業の増加です。本来であれば十分に収益を上げている企業であっても、後継者が見つからない、あるいは承継に伴う負担が大きすぎるという理由で、廃業を選択するケースが増えています。これは地域経済にとって大きな損失であり、雇用や技術の断絶を生む結果につながっています。
そして、事業承継を阻む最大の要因のひとつが「税負担」です。中小企業の株式は市場で売買されないため、純資産価値で評価されることが多く、結果として評価額が高額になりやすいという特徴があります。このため、相続や贈与の際に多額の税金が発生し、後継者にとっては大きな資金的負担となります。本来は円滑に代替わりして経営を維持すべき場面でも、税金の負担がネックとなり、承継そのものを断念せざるを得ないケースも見られます。
このように、経営者の高齢化、後継者不在、黒字廃業、そして高額な税負担という複数の問題が重なり合い、中小企業の事業承継を難しくしているのが現状です。こうした背景から、国は事業承継のハードルを下げるため、税制面の支援措置を拡充しており、その代表例が後継者の税負担を大幅に軽減する「事業承継税制」です。
最初に導入された2009年の旧制度は、「経営承継円滑化法」とともにスタートしたものです。非上場会社の株式について相続税・贈与税を猶予する仕組みでしたが、要件が非常に厳しく、実際にはほとんど利用が進みませんでした。具体的には、対象株式が最大で発行済株式の3分の2に制限されていたこと、5年間で平均8割以上の雇用維持を求められたこと、融資の担保として株式を提供できなかったこと、そして申請書類の煩雑さなどが障壁となり、利用件数は年間数百件にとどまりました。
これを受けて、国は制度の抜本的な見直しを行い、2018年に「特例事業承継税制」として大幅に改革を実施しました。この改正では、対象株式が100%に拡大され、贈与税・相続税の納税猶予が100%となり、実質的に税負担がゼロになる仕組みが整備されました。また、雇用確保要件が実質的に緩和され、達成できなくても取消されにくい制度設計へと修正されました。さらに、後継者を最大3名まで指定できるようになり、事前に「事業承継計画」を都道府県へ提出する方式が導入されるなど、使いやすさが飛躍的に向上しました。この改正こそが、政府が本気で事業承継問題に取り組み始めた大きな転換点といえます。
総じて、事業承継税制は「日本の中小企業を守るため、後継者不足と高額な税負担を解消する」という政策的課題に応える形で発展してきた制度です。いまや廃業防止、地方経済の活性化、技術や雇用の維持を支える重要な仕組みとして、さらに活用が期待されています。
ご参考:国税庁、非上場株式等についての贈与税・相続税の 納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025007-064_01.pdf







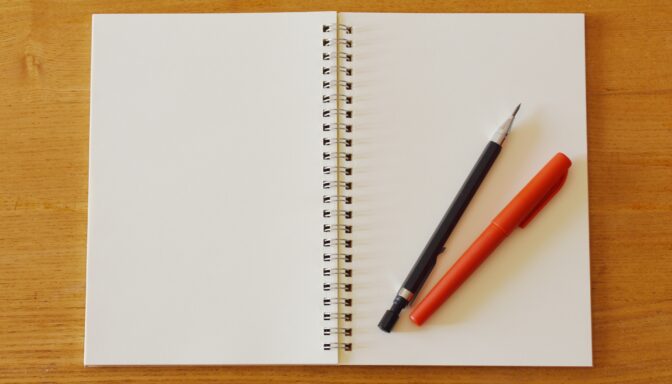




コメント